「Duolingoへの質問」へようこそ。このコラムでは言語学習者へのアドバイスをご紹介します。過去の記事はこちらをご覧ください。
こんにちは!今回は、英語以外の外国語を学習している方から多く寄せられる、英語についての質問を取り上げます。私は英語が大好きで、皆さんにもぜひ、英語がどのように進化してきたかを知り、その面白さを感じていただきいと思っています!
今週の質問
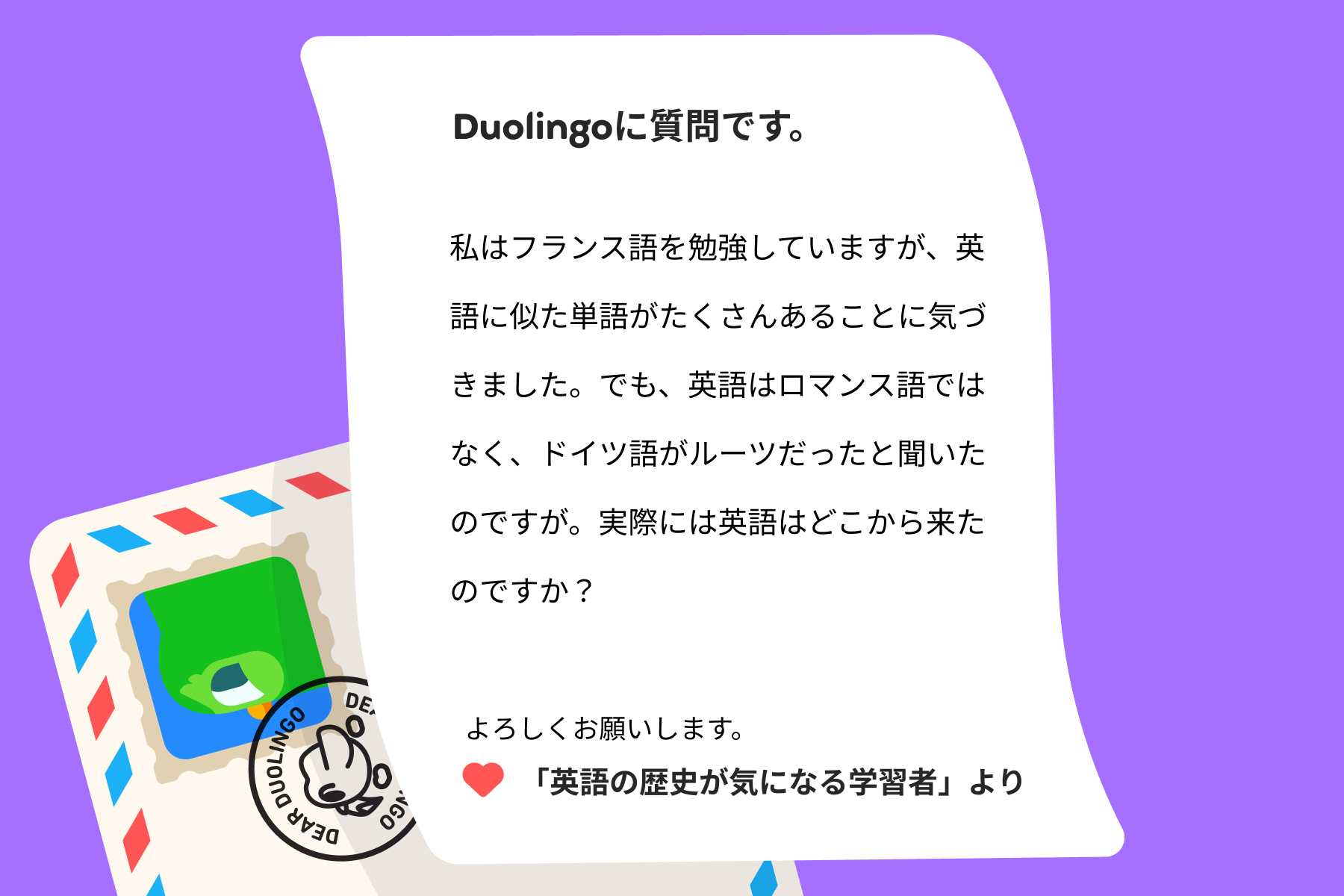
英語には、長い歴史の中で征服と敗北を繰り返し、常に異民族と接して複数言語に触れ、そこから新しい言葉を貪欲に取り入れてきたという背景があります。
実は、ある言語がいつ「始まった」あるいは「生まれた」かを明確にするのは、ほぼ不可能です! むしろ新しい言語は徐々に「生まれ」、さまざまな理由で変化していくことが多いのです。このような変化は通常、人口がある場所から別の場所に移動したり、社会の政治・宗教・文化における構造が大きく変わったりすることによって起こります。
英語は、このような出来事を幾度となく経験した結果できたものなのです!
英語はどこから来たの?
英語はロマンス語系?
古英語はどのような言語だった?
古英語、中英語、現代英語の違いは?
英語はどこから来たの?
「英語は当然、イングランドが発祥の地でしょ?」その考えは、正解です。そして、「必ずしもイングランド発祥ではないかもしれない」という考えも、ある意味正解です!
今から約1600年前、現在私たちがイングランドと呼んでいる地域の南部には、多くの集団、王国、部族が混在し、沢山の言語使われていました。ケルト語(この言語が最終的にウェールズ語となった)話者もいれば、ラテン語の方言を話すローマ兵もおり、もちろんラテン語を巧みにあやつるケルト人もいました。
つまり、あの小さな島の中で、いろいろな言語が入り乱れていたわけです。
5世紀頃、北ヨーロッパ(特に現在のドイツとデンマーク)からこの島の南部に移り住んだ集団がいくつかありました。彼らはアングル人、サクソン人およびジュート人と呼ばれる民族で、ゲルマン系であったため、すでに定住していたケルト人やローマ人とは文化や宗教、言語も非常に異なっていました。その後、アングル人の土地(当時の言葉で「Engla lond」、これが転じて「England」となった)ではアングル人とサクソン人の言語が主流となり、これが英語の起源となりました。 今日、私たちはこの言語を「古英語」と呼んでいます。
しかし、これは始まりに過ぎません。その数世紀後には、現在のスウェーデン、ノルウェーおよびデンマークにあたる地域の言語を話すスカンジナビア系の人々(つまりバイキングです!)が加わることになります。
英語はロマンス語系?
英語とフランス語(またはスペイン語、イタリア語など)との共通点がこれだけ多いことを考えると、これらの言語の起源は同一ではないか思われるかもしれません。しかし英語はロマンス系言語ではなく、ドイツ語、オランダ語、スウェーデン語、デンマーク語、ゴート語(現在は話されていない)など、北ヨーロッパの言語の流れを組むゲルマン系言語なのです。それにもかかわらず、英語の語彙はロマンス諸語、特にフランス語と重なるものが多く存在します!
というのも、英語はイングランド南部に移ってからも進化を続けたからです。おそらく最も影響力が強かったのがフランス語、正確に言えば、英仏海峡を挟んだすぐ向かい側のノルマンディー地方で話されていたノルマン・フランス語と呼ばれる方言です。
ウィリアム征服王(ノルマンディー公ウィリアム)とノルマン人がイングランドに侵入し、新しい支配階級として土地を治めるようになりました。その結果、何世紀にもわたり、英語の中にノルマン・フランス語由来の多くの語彙が流入しました。その中には、政治、地位、教育、食べ物、そして芸術のような上流階級にまつわる単語が多く含まれ、ゲルマン語の文法にそのまま取り入れられました。このようにしてフランス語の単語とゲルマン語の文法規則が混在する状態が、何世紀にもわたって受け継がれてきたたわけです!
他の言語、特にラテン語やフランス語から借用された英単語の数は膨大で、その割合は80%にも上ります。とはいえこの数字は、辞書に載っているすべての単語を対象にしたもので、普通の英語話者がめったに使わない、あるいは一度も使ったことのない単語が含まれているため、現実とちょっとかけ離れているかもしれません。そこで以下に、英語の語彙に関する他の統計をご紹介します。
- 英語で最もよく使われる100語のうち、96語は古英語から来ており、さらに3語(they, them, their)は古ノルド語に由来しますが、古英語の時点ですでに使われていました。残りの1語は、古英語でも古ノルド語でもなく、古フランス語に由来する「very」という単語です!
- スワデシュ・リスト(言語の変化に最も影響されにくい基礎語彙のリスト)にある100語のうち、88語は古英語に由来し、4語は古ノルド語、残りはラテン語とフランス語から来ています。その中には、数字、家族や親戚にかかわる用語、冠詞(theなど)、疑問詞(whatなど)、主な体の部位や生きていくのに必要な活動(「eat」「drink」など)、加えて自然や動物に関する語彙が含まれています。
- 現代英語で最もよく使われる名詞100個のうち、約半分は古英語に由来します。古英語に由来するものは44個、古フランス語・古ノルド語・ラテン語に由来し古英語の時点ですでに使われていたものが4個、そして 残りはフランス語やラテン語から来ています。
古英語はどのような言語だった?
古英語が使われていたのは1,000年以上前ですが、それにもかかわらず、古英語の実態については非常に多くのことがわかっています。叙事詩「ベーオウルフ」は書店やネットで簡単に手に入り、日本語訳まで存在します😅また、西サクソン人であったアルフレッド大王が、西サクソン方言で歴史や文学を書くことを奨励した史実は有名で、この方言が結局、古英語の標準語になりました!
現代英語の話者にとっては、古英語はまったく別の言語のように見える(または聞こえる)言語です。古英語を理解したければ、外国語を勉強するのと同じ手間をかけて古英語を勉強せざるをえません!
そして、もしあなたが英語以外の欧州言語を勉強し、英語よりも面倒なルールが多いと感じたことがあるのなら、ちょっと面白い話をお聞かせしましょう...古英語の文法も同じように面倒だったんです!
たとえば、次のように頭を悩ませた経験はありませんか?
- うわぁ、「文法上の性」って何これ? ⇒古英語には3つの文法上の性が存在しました。
- なんでまた動詞の活用がこんなにたくさんあるの?⇒ 古英語の動詞は、主語と時制に応じて活用しました。
- 普通の人でも本当に、名詞の格変化を全部言えるの?「与格」とか何とか言われても困る!⇒ 古英語の名詞には(少なくとも)4つの異なる格があり、語尾が変化しました。
古英語は、現代英語よりも他のゲルマン諸語との共通点を多く持っています。古英語の言語的な特徴は、
- 文字が異なる。古英語には、現代では使われていない文字の組み合わせや発音区別符号(アクセントのような小さなマーク)が数多くありました。また、現代英語の「th」を表す2つの異なる文字(「think」の場合の「th」に対応する文字「þ」(現在では「thorn」と呼ばれる)と、「those」の場合の「th」に対応する文字「ð」(現在は「eth」と呼ばれる)など、今では使われなくなった文字も存在します。
- 男性名詞、女性名詞、中性名詞の区別がある。古英語の名詞にはもれなく、文法上の性がありました。ただしこの文法上の「性別」は、ほとんどの場合、理屈では説明できません。たとえば「妻」や「女性」を意味する単語「wīf」は中性名詞で、「女性」を意味する別の単語「wīfmann」はなんと、男性名詞でした!
- 名詞に4種類の「格」があった。古英語の名詞は、文中の役割(直接目的語なのか、主語なのか、など。これを「格」と言います)によって変化し、名詞ごとに主格、対格、属格および与格という、4つの異なる形がありました。また、単数か複数に加えて名詞の性(男性、女性、中性)によっても格変化が異なり、語尾がいちいち違っていたのです🤯
- フォーマルな代名詞とインフォーマルな代名詞:古英語では、相手に丁寧な口調で話すか、それとも馴れ馴れしく話しかけるかどうかによって「you(あなた)」を表す言葉が違いました。「þu」がインフォーマルな表現、「ge」がフォーマルな表現です(結局どちらが廃れてどちらに統一されたかを、当ててみてください!)。
古英語、中英語、現代英語の違いは?
さて、古英語の歴史と言語学的な特徴を少し見てきましたが、中英語と現代英語についても少し紹介しておきましょう。
中英語
時期:大まかに言って11世紀から15世紀。中英語の時代が始まったのは、1066年のノルマン人の侵攻からであるとされています。
変化点:文法上の性と、ほとんどの名詞の格変化が消失しました。ただし、1つの格(属格と呼ばれ、所有や所属を表すのに使われる)だけは残り、誰かに属するものであることを示す場合に「~es」をつけるルールができました(たとえば中英語の「a sowes erys」は、現代英語では「a sow’s ears(メス豚の耳)」にあたります)。格がほぼなくなったかわりに、語順の決まりはより厳しくなっています。また、アングロサクソン系の語彙の多くが、ノルマン・フランス語やそれ以降のフランス語の単語に取って変わりました。さらに大母音推移(Great Vowel Shift)が始まり、これまでひっそりとした存在だった「母音」が、中英語で急激に変化し始め、その半数は数世紀の間にまったく新しい発音となってしまいました。学習者を大いに悩ませている英語のスペルと発音の矛盾、特に母音の矛盾は、まさにこの大母音推移の産物なのです。
何から影響を受けたか:この時期の英語は、フランス語の猛烈な洗礼を受けました。ラテン語を起源とする語彙の多くは、このときにフランス語を通じて英語に取り入れられています。そのため、昔ながらの英語の単語(ghost, house, cow)と、フランス語起源のより高尚な単語(spirit, domicile, beef)が同義語として共存するようになりました。ときには、何世紀もの間に、あるいは異なるフランス語の方言から、2度にわたってフランス語の単語が取り込まれたこともあります。その結果、英語にはフランス語系の類義語がいくつも残ることになり、たとえば「cattle(家畜)」はノルマン・フランス語、「chattel(家畜や奴隷を含む動産)」は何世紀も後の内陸のフランス語を起源としています。
中英語で書かれた代表作:ジェフリー・チョーサーの『カンタベリー物語』や、作者不詳の『ガウェイン卿と緑の騎士』(ファンタジー映画の『緑の騎士』の原作)。
現代英語
時期:大まかに言って15世紀から今日まで。チョーサーが亡くなった頃が、中英語と現代英語の境目にあたります。つまり私は今、シェイクスピアが400年前に書いた英語と大差ない英語を書いているわけです。とはいえ、数多くの変化も起こりました。一般的に、言語の変化はゆっくりと段階的に進むプロセスであることを覚えておきましょう。
変化点:古ゲルマン語の属格(所有や所属を表す格)の語尾である「~es」がさらに変化し、現代の「child’s toy(子供のおもちゃ)」や「team’s win(チームの勝利)」のときに使う「~’s」となりました。この約200年の間に、スペル表記が標準化され、動詞の活用は大幅に減少し、ほとんどの動詞で現在形が2つ(「talk/talks」「see/sees」など)、過去形が1つか2つ(「talked/talked」「saw/seen」など)に集約されています。また、多くの新興の英語方言が世界中で生まれ、定着しました。
何から影響を受けたか:植民地、奴隷制度、グローバリゼーションなど。イギリスの植民者たちが世界中に広がり定住するにつれて、英語は世界各地で勢力を伸ばし、多くの場合、その土地本来の民族、言語、文化は衰退を余儀なくされました。支配階級の言語として、また時には共通語として、英語は先住民族の単語や文法を取り入れた新たな言語に生まれ変わり、時には他の言語にも影響を与え(フランス語やタイ語のような地理的に離れた場所の言語にも、英語の単語は数多く見受けられます)、新しいピジンやクレオール(ジャマイカン・クレオールやカメルーン・ピジン英語のような)を生み出しました。また、世界各国から人が集まる場所(たとえば私がバックパッカーだった頃によく泊まったホステル)でも重宝されています。
現代英語で書かれた代表作:ウィリアム・シェイクスピアの戯曲や詩、ビリー・ホリデイの音楽(ビリー・アイリッシュも!)、「Duolingoへの質問」英語版。
英語の変化をたどってみよう
各時代の英語の例文を比較してみれば、その違いは簡単に理解できます!一例として、古い時代から翻訳され受け継がれてきた文章(キリスト教の「主の祈り」)を使い、変化の各段階を見てみましょう。
(訳注:「主の祈り」は、キリスト教徒にとって最も基本的な祈りの文句の1つで、「天にまします我らの父よ、願わくはみ名をあがめさせたまえ。み国を来たらせたまえ」を意味します。)
| 「主の祈り」の文章 | ここに注目 | |
|---|---|---|
| 古英語 | Úre Fæder, þú þe eart on heofonum sí þín nama gehálgod. Tócume þín ríce. |
アクセント記号と2つの見慣れない文字(þとæ)が使われている。「王国」を意味する「Ríce」は、ドイツ語の「Reich」からさほど離れていない。 「ge~」と「tó~」は接頭辞の一種であることを知れば「gehálgod」が「hallowed(神聖な)」、「tócume」が「come(来る)」に近いことがわかる。 |
| 中英語 | Oure fadir that art in heuenes, halewid be thi name. thi kyngdoom come to. |
かなり現代英語と似た形に! スペルのルールが変わり、接頭辞や接尾辞のほとんどが消滅したり、短縮されたりした。古英語で使われていた「ríce」という単語は、この時点で別の古英語「kyngdoom」に置き換わっている。 |
| 初期の現代英語 | Our father which art in heauen, hallowed be thy name. Thy kingdome come. (訳注:これを今の言葉で言い換えると「Our Father, who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come」となります。) |
スペルがあちこち違っていても、ネイティブ話者ならば容易に理解できるレベル。「thy」は「汝の」という意味、「art」はbe動詞の活用形で、現在、通常の会話ではほとんど見られないが、宗教的な文章ではたまに使われている。 |
英語は言語のるつぼ
多くの言語がそうであるように、英語もまた多くの変化と適応を経て今日の形となりました。なぜなら、英語をコミュニケーションに使っていた人々の文化や政治が変化したり、他国を征服して言語圏を広げたり、逆に征服されて言語の変化を余儀なくされたりしたからです。
その結果、今私たちが使っている英語は、世界中からの影響を受けたものとなっています。だから私は、イギリスのバンド、モダン・イングリッシュが「I'll stop the world and melt with you(僕は世界を止めあなたと一体になる)」と歌うのを聴くと、英語という言語のあり方と同じだなぁ、としみじみ思うのです。
言語の裏側を知って学習に役立てたい方は、dearduolingo@duolingo.comまでどんどん質問をお寄せください!
